建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307
業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください
中国語・韓国語対応可
新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします
一人親方・個人の建設業者の確定申告のしかた
消費税は原則課税と簡易課税のどちらがよい?
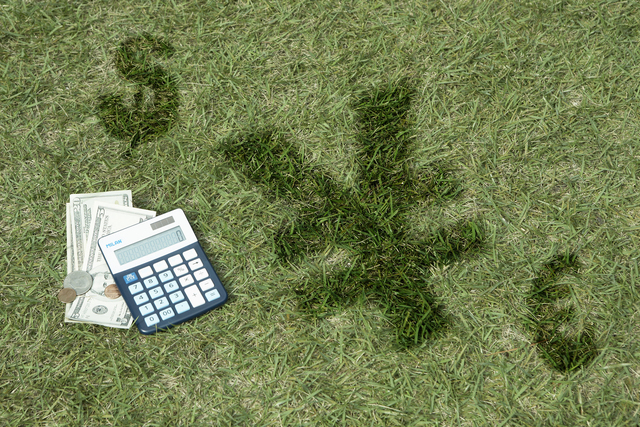
事業者は、売上が1,000万円を超えるようになると消費税の課税事業者になり、消費税を納めなくてはならないようになります(詳しくは、個人事業の税金②【消費税】をご覧ください)。
消費税の計算方法は、原則課税と簡易課税の2種類があります。
簡易課税を選択したい場合には、事前に届出書を提出しなければなりません。
原則課税の計算方法
売上先に請求をする際、本体価格に消費税を上乗せして請求していると思います。
(ちなみに、消費税の免税事業者であっても、消費税を請求することは問題ありません。)
消費税の課税事業者は、この売上先から預かった消費税を国に納める必要があります。
しかし一方で、経費を支払う際は消費税も同時に支払っているはずです。
経費にかかる消費税は、消費税の納税額の計算上、納税額から差し引くことができます。
(ただし、保険料や租税公課など消費税のかからない経費もありますのでご注意ください。)
つまり、消費税の納税額の計算は、預かった消費税(売上にかかる消費税)と支払った消費税(経費にかかる消費税)の差額を納付することが原則になります。
これが、消費税の原則課税の計算方法になります。
原則課税は、文字どおり消費税の原則的な計算方法になりますので、簡易課税を選択するための届出をしない限りは自動的に原則課税が適用されることになります。
簡易課税の計算方法
簡易課税の場合は、売上にかかる消費税の計算については原則課税と同じなのですが、経費にかかる消費税の計算が原則課税と違います。
簡易課税においては、経費にかかる消費税が実際にいくらなのかは関係なく、売上にかかる消費税に一定の率(みなし仕入率)を乗じた金額を支払った消費税とみなして消費税の納税額を計算します。
みなし仕入率は、下記のように業種により異なっております。
| 業種区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
|---|---|---|
| 第一種事業 | 90% | 卸売業 |
| 第二種事業 | 80% | 小売業 |
| 第三種事業 | 70% | 建設業、製造業ほか |
| 第四種事業 | 60% | 飲食業、手間請負 |
| 第五種事業 | 50% | サービス業ほか |
| 第六種事業 | 40% | 不動産業 |
建設業の場合は、基本的には第三種事業に該当しますが、一人親方など手間請負で仕事をしている場合には第四種事業に該当しますのでご注意ください。
簡易課税を適用する場合、消費税の納税額の計算としては下記のようになります。
消費税の納税額=売上にかかる消費税-売上にかかる消費税×みなし仕入率
つまり、経費にかかる消費税は一切考慮せず、売上のみで消費税の計算ができてしまいます。
そのため、原則課税よりも簡単に消費税の納税額を計算できるのが特徴です。
複数の事業を営んでいる場合の簡易課税の計算
簡易課税の計算は、売上の業種ごとにみなし仕入率を適用するのが原則になります。
そのため、たとえば第三種事業の売上が1,500万円(消費税120万円)、第四種事業の売上が500万円(消費税40万円)の場合には、下記のようにそれぞれに対応するみなし仕入率を乗じる必要があります。
消費税の納税額=(120万円-120万円×70%)+(40万円-40万円×60%)
=52万円
ただし、複数の事業を営んでいる場合であっても、そのうち1つの事業の売上が売上全体の75%以上である場合には、その75%以上の事業におけるみなし仕入率のみを使ってもよいという特例があります。
たとえば先ほどの例でいうと、売上全体2,000万円(=1,500万円+500万円)に対して第三種事業の売上が1,500万円ですから、売上全体の75%以上(1,500万円÷2,000万円≧75%)が第三種事業ということになります。
そのため、下記のように特例を使う(みなし仕入率70%のみを使う)ことも可能です。
消費税の納税額=(120万円+40万円)-(120万円+40万円)×70%
=48万円
今回の場合は特例の方が納税額が低くなりますので、特例を選択するのが通常です。
簡易課税を選択するための手続き
簡易課税を選択する場合には、消費税簡易課税選択届出書を提出する必要があります。
簡易課税選択届出書の提出期限は、簡易課税の適用を受けようとする年の前年末までとなっております。
つまり、たとえば29年から簡易課税の適用を受けたいのであれば、28年12月末までに簡易課税選択届出書を提出しなければなりません。
また、簡易課税を受けるためには、基準期間(前々年)の売上が5,000万円以下でなければなりません。
なお、簡易課税の適用をやめたい場合には、消費税簡易課税不適用届出書を提出する必要がありますが、簡易課税は一度選択すると2年間は原則課税に変更することができませんので、その点も考慮して簡易課税を選択するようにしましょう。
原則課税と簡易課税のどちらを選択するか?
以上が原則課税と簡易課税の計算方法と諸手続きになりますが、原則課税と簡易課税のどちらを選択するかは、原則課税の計算が面倒なので簡易課税を選択するということでもよいのですが、基本的には消費税の納税額が低くなる方を選択した方がよいでしょう。
とは言っても、簡易課税の選択届出書は前年末まで提出しなければなりませんので、原則課税と簡易課税のどちらの方が納税額が低くなるかを予測して選択するしかありません。
予測の方法としては、前年以前の損益計算書をもとに消費税の納税額を計算してみるのが一般的です。それにより、自分は原則課税と簡易課税のどちらがトクかが何となく見えてくると思います。
ただ、簡易課税は最低2年は継続しなければなりませんので、判断を間違えた場合のダメージが大きくなってしまう可能性があります。
そのため、判断に迷われた場合や、どちらを選択しても納税額がそれほど変わらなそうな場合は、原則課税を選択した方がよいでしょう。
当事務所のオススメサービス
一人親方・個人建設業者等の確定申告

確定申告には、白色申告と青色申告があり、青色申告には10万円控除と65万円控除があります。
青色申告65万円控除を行えば、最低でも15万円の所得税、住民税、国民健康保険料を安くできます。
青色申告65万円控除のための帳簿作成を代行するだけでなく、そのサポートをすることも可能です。
お問合せはこちら

新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします




