建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307
業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください
中国語・韓国語対応可
新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします
建設業の経営分析
資本や資産の回転効率を示す活動性分析
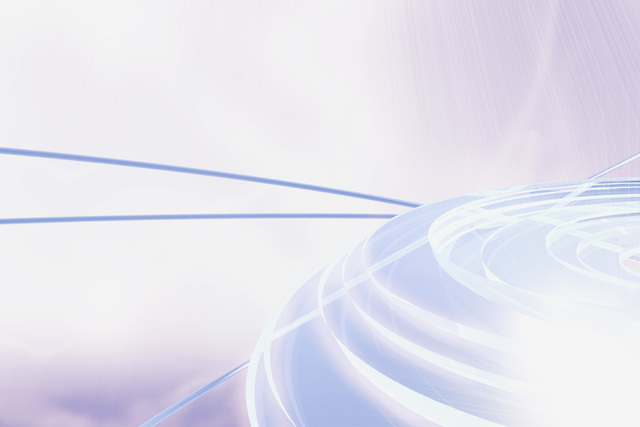
活動性の分析とは、企業における資本やその運用である資産が、一定期間においてどれだけ運動したかを分析するものになります。
活動性分析は、収益性分析と密接な関係にあります。
収益性分析において、資本利益率は下記の算式により計算されます。
資本利益率=利益÷資本×100
また、資本利益率は、下記のように分解して検討することができます。
資本利益率=(完成工事高÷資本)÷(利益÷完成工事高)×100
「完成工事高÷資本」は資本回転率、「利益÷完成工事高」は完成工事高利益率をそれぞれ示します。資本利益率や完成工事高利益率は企業の収益性を示す指標になり、資本回転率は企業の活動性を示す指標になります。
つまり、収益性は活動性により支えられているということができ、活動性を高めることは収益性を高めることにつながります。
なお、収益性分析と同じく、活動性の分析の基礎となる完成工事高と資本(資産)については、完成工事高が1会計期間において測定されたものであることに対し、資本(資産)は期首や期末の時点において測定されたものになりますので、資本(資産)の額については、下記のように期首から期末までの期間における平均にすることが必要になります。
資本=(期首資本+期末資本)÷2×100
活動性の分析に用いられる指標は回転率と回転期間
活動性の指標としては、回転率と回転期間が用いられます。
回転率とは、一定期間、通常であれば1年間において資本や資産が何回入れ替わったかをいいます。回転期間とは、資本や資産が1回転するのに要する期間をいいます。
回転率だけでは1年間の資本や資産の回転数しか分かりませんが、回転期間を分析することにより、資本や資産が発生してから消費されるまでの期間が把握できますので、回転の適正性を知ることにつながります。
回転率と回転期間は、互いに逆数の関係にあります。
下記のように、回転率が3回であれば回転期間は4か月になりますし、回転率が4回であれば回転期間は3か月になります。
回転期間=12か月÷回転率(3回)=4か月
回転期間=12か月÷回転率(4回)=3か月
活動性を示すそれぞれの指標の分析方法
活動性を示す回転率については、大きく3区分に分けることができます。
- 資本回転率・・・総資本回転率、経営資本回転率、自己資本回転率
- 資産回転率・・・棚卸資産回転率、受取勘定回転率、固定資産回転率
- 負債回転率・・・支払勘定回転率
以下、それぞれの回転率の分析方法について解説いたします。
総資本回転率
総資本回転率は、下記の算式により計算します。
総資本回転率=完成工事高÷総資本×100
総資本回転率は、総資本の活動効率や回収程度をあらわす指標になります。
総資本回転率が高いほど、総資本が効果的に利用されたことになります。
建設業情報管理センターのデータによると、平成26年度における建設業全体の総資本回転率は1.83回となっております。
経営資本回転率
経営資本回転率は、下記の算式により計算します。
経営資本回転率=完成工事高÷経営資本×100
経営資本回転率とは、企業の営業活動に直接投下された資本の運用効率をあわらす指標になります。
経営資本回転率が高いほど経営資本利益率も高くなりますので、企業の営業活動にもとづく収益性を分析する上で重要な指標になります。
自己資本回転率
自己資本回転率は、下記の算式により計算します。
自己資本回転率=完成工事高÷自己資本×100
自己資本回転率とは、自己資本が1年間に何回転したかを示すものになりますので、自己資本の運用効率をあらわす指標になります。
自己資本回転率が高いほど自己資本の運用効率が高いため、基本的には自己資本回転率は高い方が良好であるということができます。
しかし、過度に高い場合は、自己資本に対して完成工事高が大きすぎるということになりますので、他人資本に依存しすぎている、つまり営業過多の状態であるという見方になります。
建設業情報管理センターのデータによると、平成26年度における建設業全体の自己資本回転率は7.88回となっております。
未成工事支出金回転率
未成工事支出金回転率は、下記の算式により計算します。
未成工事支出金回転率=完成工事高÷未成工事支出金×100
未成工事支出金回転率は、未成工事支出金が回転する速度をあらわす指標になります。
未成工事支出金回転率が高いほど、未成工事支出金の回転期間が短く、工事原価が少ないことをあらわしますので、通常であれば未成工事支出金回転率が高いほど良好であると考えられます。
しかし、未成工事支出金が少なすぎる場合には、一定の営業活動を維持することができないため、未成工事支出金回転率が高ければよいとは必ずしも言い切れません。
なお、建設業における棚卸資産としては、未成工事支出金のほかに材料貯蔵品がありますが、建設業では工事用の材料は必要の都度購入されるのが通常のため、材料貯蔵品の回転率を測定することはあまり意味をもちません。
建設業情報管理センターにおいては、材料貯蔵品や販売用不動産を含めて棚卸資産回転率を測定しており、平成26年度における建設業全体の棚卸資産回転率は72.35回となっております。
受取勘定回転率
受取勘定回転率は、下記の算式により計算します。
受取勘定回転率=完成工事高÷(受取手形+完成工事未収入金)×100
受取勘定回転率は、受取手形や完成工事未収入金が回収される速度をあらわす指標になります。
受取勘定回転率により、受取手形や完成工事未収入金の回収状況が分かります。
この比率が高いほど回収速度が速いことになり、一方、この比率が低いほど回収速度が遅く売上債権が固定化してしまっていることになります。
また、受取勘定回転率を計算する上では、下記のように未成工事受入金を受取勘定からマイナスして計算することも有用です。
それにより、正味の受取勘定にもとづく受取勘定回転率を分析することができます。
受取勘定回転率=完成工事高÷(受取手形+完成工事未収入金-未成工事受入金)×100
東日本建設業保証のデータによると、平成26年度における東日本の建設業全体の受取勘定回転率は18.62回となっております。
固定資産回転率
固定資産回転率は、下記の算式により計算します。
固定資産回転率=完成工事高÷固定資産×100
固定資産回転率は、固定資産に投下された資本の運用効率、つまり固定資産の利用度をあらわす指標になります。
固定資産が有効に利用されるほど完成工事高が増加し、固定資産回転率が高くなることになりますので、固定資産の投資が適正かどうかを分析することができます。
建設業情報管理センターのデータによると、平成26年度における建設業全体の固定資産回転率は12.67回となっております。
支払勘定回転率
支払勘定回転率は、下記の算式により計算します。
支払勘定回転率=完成工事高÷(支払手形+工事未払金)×100
支払勘定回転率は、支払手形や工事未払金の支払状況の速度をあらわす指標になります。
支払勘定回転率が低いほど支払手形や工事未払金の回転期間が長いことになりますので、資金繰り上は支払勘定回転率は低い方が良いことになりますが、過度に長い場合は支払いが滞っていることも考えられますので、正常な範囲の比率である必要があります。
東日本建設業保証のデータによると、平成26年度における東日本の建設業全体の支払勘定回転率は14.31回となっております。
まとめ
以上、活動性分析の手法についてご紹介いたしました。
活動性の分析は、企業活動が効率的に回っているかを分析する上で重要な指標になります。
会社の現状把握や今後の成長のために、活動性分析を役立ててみてはいかがでしょうか。
当事務所のオススメサービス
税理士顧問・決算申告

建設業に強い税理士が、経理面・税金面からお客さまの経営をサポートいたします。
建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。
融資に強い決算書を作成し、合理的な節税が行えるようなサポートをしてまいります。
お問合せはこちら

新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします




